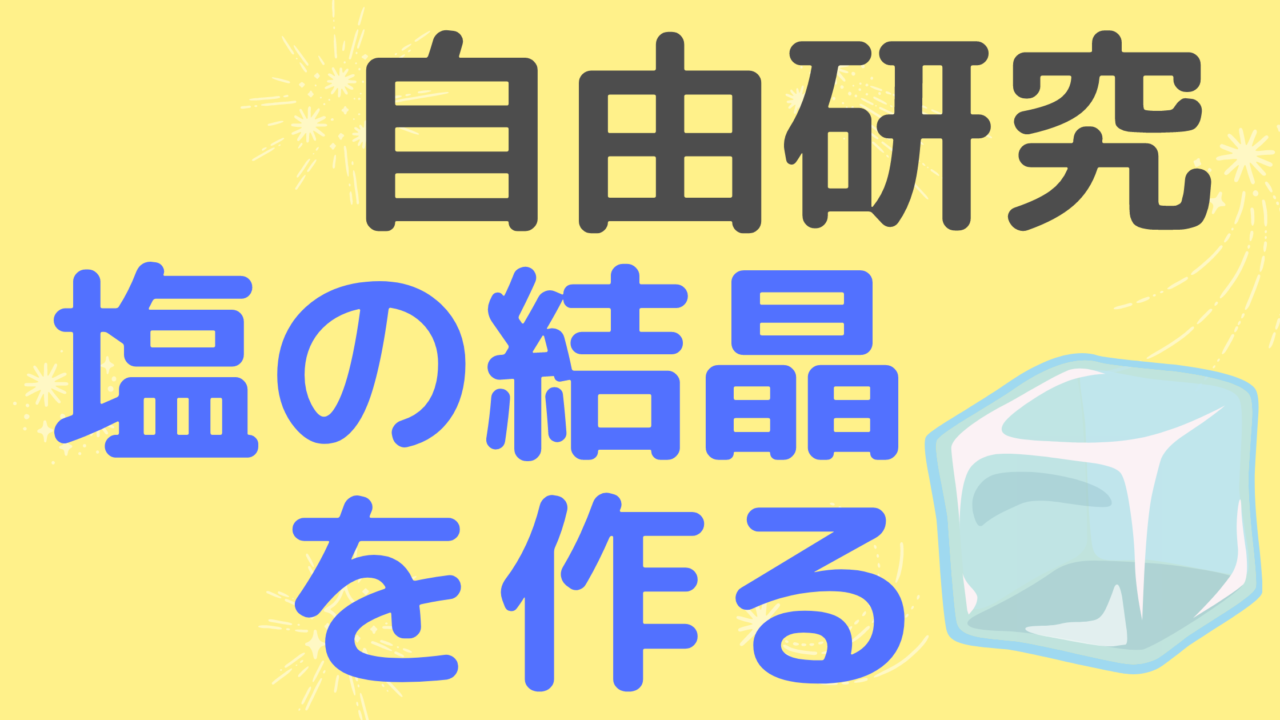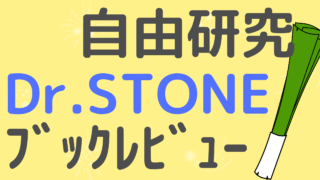夏は熱中症対策に水分と塩分の補給が大事。
一方で、特に大人は塩分のとりすぎに注意。
塩ってなんなんでしょう。
食べ物のしょっぱさを感じる塩味、その正体は食塩(塩化ナトリウム)です。
海水がしょっぱいのも、海水には食塩が溶け込んでいるからです。
夏休みも終盤、家にあるもので簡単にできる実験として、
『塩の結晶』を作る方法を紹介します。
自由研究、もう済んだ方も、これからの方も
ご覧いただければうれしいです。
それではよろしくお願いします。
スポンサーリンク
準備
- コップ
- お皿 (底が平たいもの、暗い色のほうが良い)
- 水
- 食塩
- はかり (無くてもOK)
実験のやり方
- コップに水を20g量った
- 料理用の塩を6g量って、コップの水に加えた
- スプーンでかき混ぜて、塩を溶かした
(1分くらい) - 作った塩水をお皿の上にたらした
(今回は黒いプレートを使いました) - 約6時間待った
(今回は26℃、湿度60%の屋内で乾かしました)
けけ博士
今回作った塩水の濃度は6.25%。海水が3.4%なので、海水の2倍弱の濃さの塩水を作ったことになります。
結果
- 塩水は透明だった
- 約6時間後、水がすべて蒸発した
- ところどころに、塩の結晶が散らばっていた
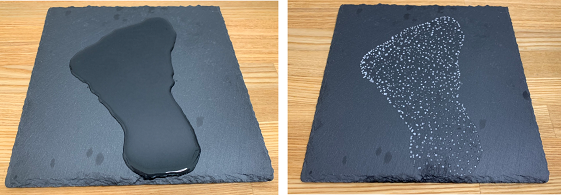
(右) 塩水が乾いたあとの様子。
- 塩の結晶の形はサイコロ状(立方体)だった
- 結晶の大きさは1~2ミリのものがほとんどだった
- これは水に溶かす前の塩の粒より大きかった
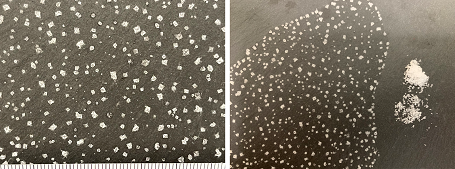
(右) もとの塩
考察 (わかったこと)
- 塩を水に溶かすとき、溶ける量には限界がある
- お皿の上で水が蒸発すると、水の量が減って、
溶けきれなくなった塩が結晶として出てくる - 塩は”ナトリウムの粒”と”塩素の粒”が交互にならんで、
サイコロ状のカタチをしている (下図) - これが縦・横・高さと重なっていくので、
できあがった結晶もサイコロ状になる
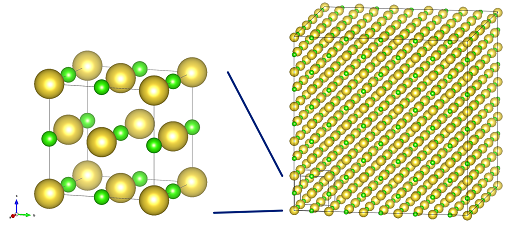
まとめ
家にあるもので簡単にできる『理科の実験』を紹介しました。
塩は水に溶けると見えなくなりますが、
水が蒸発すると、再び姿を現しました。
乾燥させるときの温度や湿度が違うと、
乾く速さが変わって、できあがる結晶の大きさが変わります。
もっと大きい結晶を作るためにはどうしたら良いのでしょうか。
けけ博士
調味料の塩も、作り方は同じです。海水を陸にくみ上げて、太陽と風で乾かして作ります。
この他にも、例えば、
- 桶に張った水に、卵や野菜(イモなど)を沈める
- 水に徐々に塩を溶かしていく
- 卵や野菜が浮かんでくる様子を観察
などして、『物の密度を比べてみる実験』も良いかも知れません。
けけ博士
グッドラック!
最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
Twitter(@kekehakase)をやっています。
今後も有益な情報を発信していきますので、
フォローしていただけたら嬉しいです。