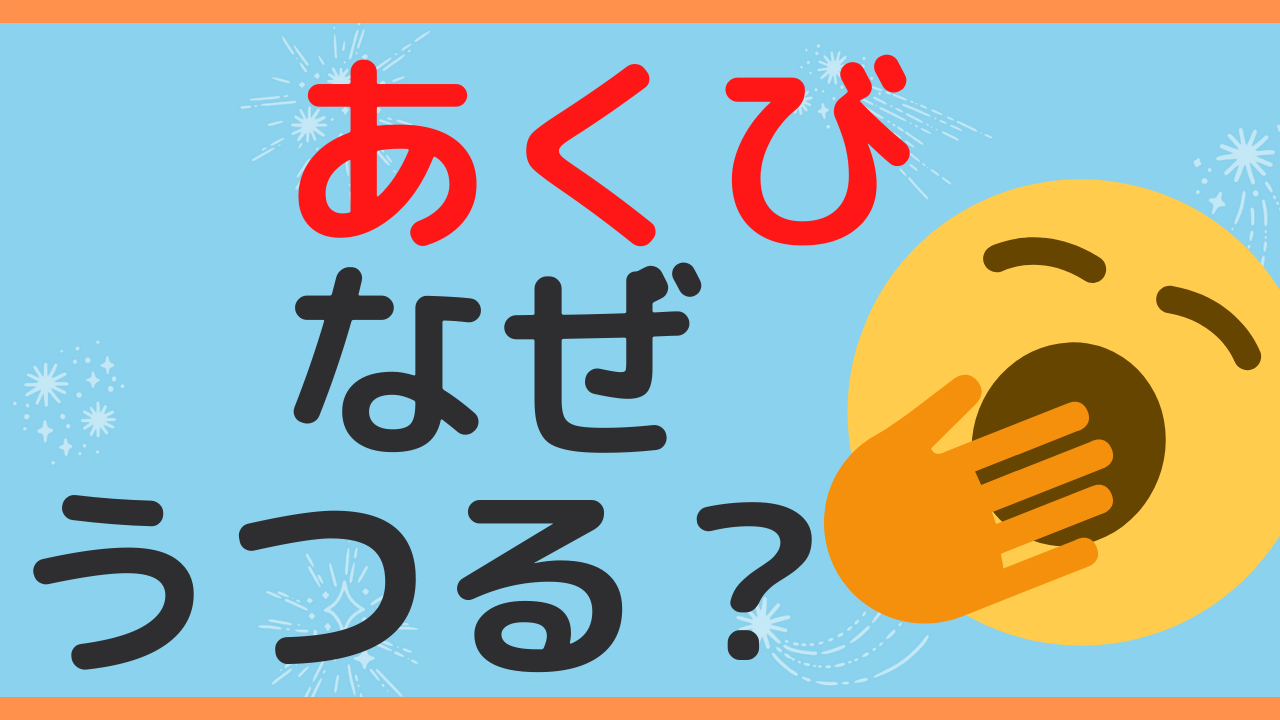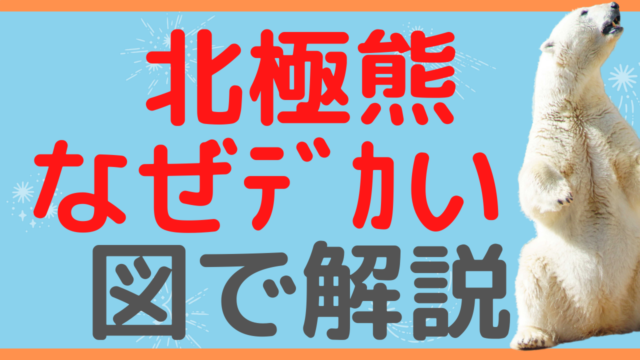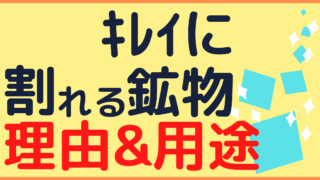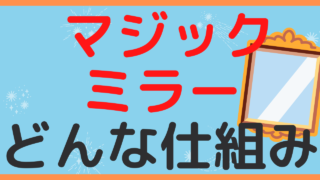目の前であくびされたら、自分もあくびしちゃいますよね?
“伝染性”のあくびは実際にある現象です。
なんでうつるのでしょう?それはあなたが優しいからです。
この記事では、
- 共感性の高い人ほど、あくびがうつりやすいこと
- 赤ちゃんや乳幼児は未だあくびがうつりにくいこと
- そもそも、あくびはなんででるのか?
について、研究結果を交えて紹介します。
それでは宜しくお願いします。
研究①:【共感性の高い人】あくびがうつりやすい
ニューヨーク州立大学の心理学者スティーブン・プラテック教授らの研究結果を紹介します。
あくびをしている人のビデオを見せられたとき、
人々がどう反応するか調査しました。

実験の結果、あくびがうつらない人は
「他人の立場に立ってものを考えることが苦手」
とわかりました。
あくびがうつる人はkind people (優しい人)であると報告しています。
あくびをしている他人の気持ち(状態)に共感することで、
無意識に物まねしてしまう?と考察しています。
なんか考察よわいですよねww
ただ、一般に共感行為が苦手とされている統合失調症患者は、
ほとんどあくびがうつらないらしく、
それもこの研究チームの主張をサポートしているようです。
あくびの研究をすることで、
他の病気についての理解が深まるのは興味深いです。
研究②:【赤ちゃん・乳幼児】あくびがうつりにくい
スコットランド・スターリング大学の心理学者ジム・アンダーソン博士らによる研究を紹介します。
5才以下の赤ちゃんや乳幼児は、
自分であくびすることはあっても、n
人からあくびがうつることはないことを確かめました。

あくびがうつり始めるのは5歳ごろからとのこと。
そして、11歳になると大人と同じくらい
あくびをうつされる、と報告しています。
研究①で、「共感力」が高い人ほど、
あくびをうつされやすいことを紹介しました。
しかし、この研究②では乳幼児はお母さんからも
あくびをうつされない、と報告しています。
お母さんと言えばきっと赤ちゃんが
1番共感しやすい相手ですよね。
さて、脳に前頭葉という場所があります。
「社会性」「共感」「コミュニケーション」「感情のコントロール」をする器官です。
人間は6歳までに脳の90%ができますが、
前頭葉は6歳以降も(10代になっても)成長を続ける部位です。
「あくびの伝染」という心理学の研究が、
「脳の発達」という脳科学の研究を裏付けにして理解される、
分野の横断がおもしろいですね。
誰かが「眠くなってきたー」とあくびをすると、
それに共感するように脳からカラダに伝達して
「たしかに眠いね。そろそろ寝ようかー」とあくびがうつる。
私達が社会的動物であることを確認できる現象かも知れません。
③あくびの根本原因
未解明
そもそもなぜあくびは出るのか?
これはまだはっきりとはわかっていないようです。
自分が子どものときには「酸素不足だとあくびが出る」と教わりました。
今でも一般常識でしょうか。
ただ、これは実験で否定されています。
酸素を多くしたときと、二酸化炭素を多くしたとき、
あくびをする回数は変わらないことがわかっています。

あくびの効果
それでも、あくびをすると、たくさん空気を吸って吐くことはたしかですよね。
あくびの効果としては、
- 熱を持った脳を冷やす
- 耳の中の気圧を外気圧に合わせる
が知られています。
頭や首を氷で冷やしておくと、あくびは出ないそうです。
山や飛行機など気圧の低いところであくびをすると「耳抜き」ができます。
まとめ
この記事では、
- 共感性の高い人ほど、あくびがうつりやすいこと
- 5歳以下の子どもはあくびがうつりにくいこと
- 脳の共感性をつかさどる部分は、6歳以上も成長を続けること
- あくびが出る根本原因はいまだ解明されていないこと
を紹介しました。
あくびのような日常的行為が『心理学』『脳科学』『動物行動学』など、
色んな分野の研究に関与していることは、おもしろいです。
例えば、先輩が話してるときに、自分があくびしちゃったら、失礼ですよね。
でも、ボス的存在の上司や先生が先にあくびをしてくれたら、
我慢せずきっと自分もあくびうつっちゃいます。
こういう現象を客観的に考えることは、
自分が社会的動物であることを考えることにつながります。
あくびしちゃいけない場面であくびしたくなってきたとき、
自分の”動物性”や”人間性”について考えてみることも、
考えの幅を広げる練習にかるかもしれません。
最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
Twitter(@kekehakase)をやっています。
今後も有益な情報を発信していきますので、
フォローしていただけたら嬉しいです。