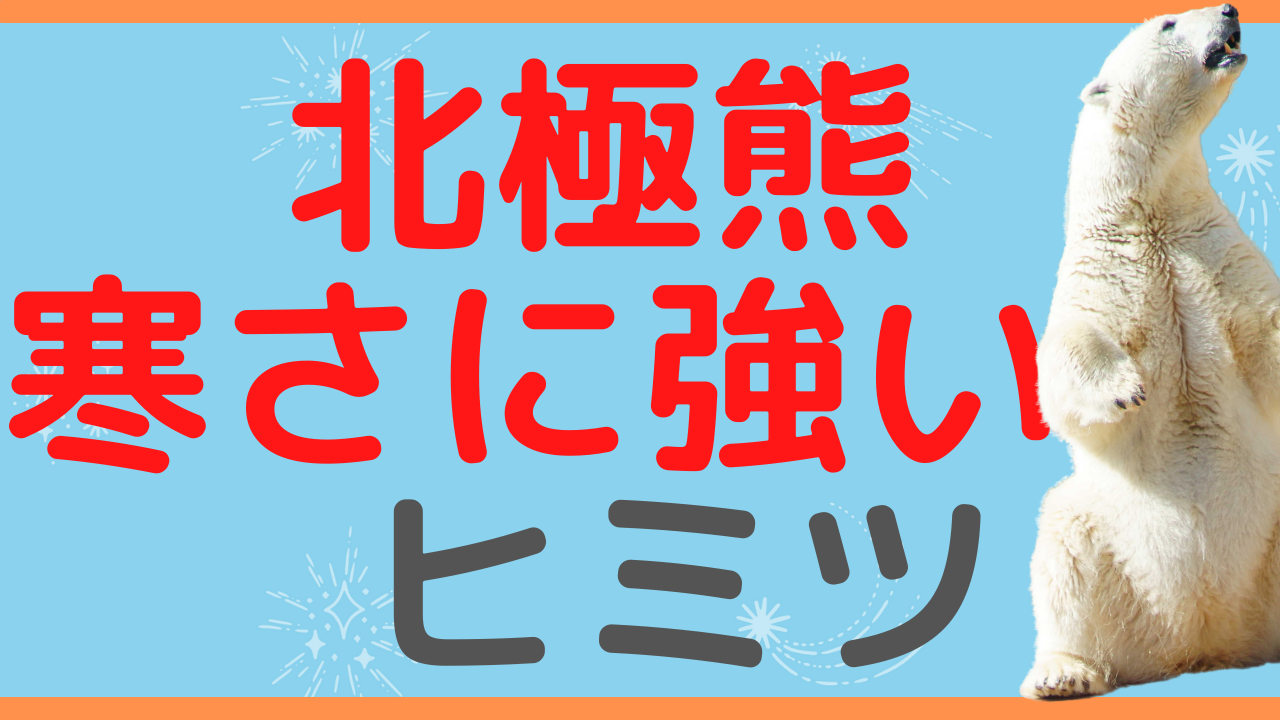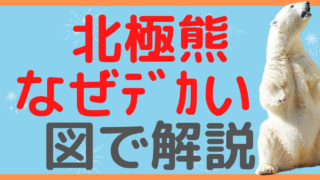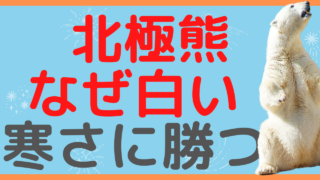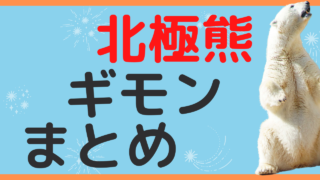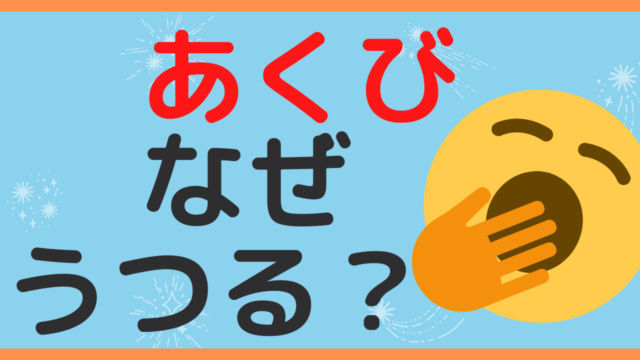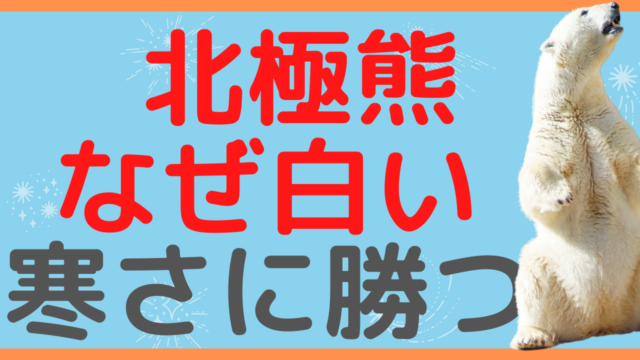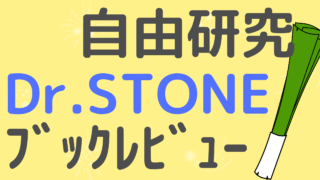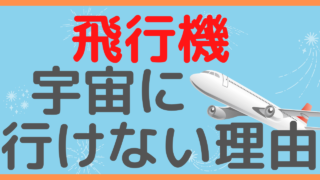ホッキョクグマやシベリアトラ、寒い地域に棲む動物は大きいですよね。
暑いところに棲むキツネの耳が長かったり、
サルのしっぽが長かったりするのも見たことがあると思います。
どうしてなんでしょうか。
結論から言うと、
・寒いところで、カラダの熱が出ていくのを抑えるため
・暑いところで、カラダの熱が出ていくのを速めるため
です。
順番に説明したいと思います。
それでは宜しくお願いします。

【ホッキョクグマ】なぜデカい?【気温と動物の大きさ】
例えば40℃のお湯を
・コップに少し入れたとき
・湯舟にたくさん入れたとき
先に冷めるのはどちらでしょう。
小さい方が冷めやすい、大きい方がずっと温かいままです。
・小さい方が、熱を放出するのに得 → 暑いとこで有利
・大きい方が、熱を貯めとくのに得 → 寒いとこで有利
なんとなくわかりますよね。
それではクマの大きさと棲んでる地域を見てみましょう。

寒いところに棲んでいるクマの方が大きい。
暑いところに棲んでいるクマの方が小さい。
法則に当てはまっています。
『同じ動物なら寒いところに棲む仲間の方が大きい。
暑いところに棲む仲間の方が小さい』
この法則を『ベルクマンの法則』と言います。
暑いところに棲む動物は耳が長い?
キツネの例を見てみましょう。

寒いところに棲むキツネほど、耳が短く、
温かいところに棲むキツネほど、耳が長くなっています。
耳が長いほど、表面積が大きいので熱を放出しやすく、
耳が短いほど、表面積が小さいので熱の放出を抑える効果があります。
『暑いところに棲んでいる動物の方が、耳やしっぽ、脚など、
カラダから出ているパーツが、細長くなる』
この法則を『アレンの法則』と言います。
まとめ
・同じ種類の動物なら、寒い地域に棲む仲間の方が大きく、暖かい地域に棲む仲間の方が小さくなる
・寒い地域に棲む仲間の方が耳やしっぽが長く、暖かい地域に棲む仲間の方が短いことを解説しました。
自然淘汰や進化についてはこの入門書が読みやすくて学びが多いです。
おすすめの教養本のひとつです。
最後までご覧いただき、
ありがとうございました。
Twitter(@kekehakase)をやっています。
今後も有益な情報を発信していきますので、
フォローしていただけたら嬉しいです。